食物アレルギー
「本来は体に害を与えない食べ物を異物と勘違いし、免疫反応が過敏に働いてしまう現象」です。その結果、蕁麻疹(じんましん)やかゆみ、咳などが引き起こされます。
時に、アナフィラキシー(発症後、極めて短い時間のうちに全身にアレルギー症状が出る反応のこと。血圧の低下や意識障害などを引き起こし、場合によっては生命を脅かす危険な状態になることもあります。

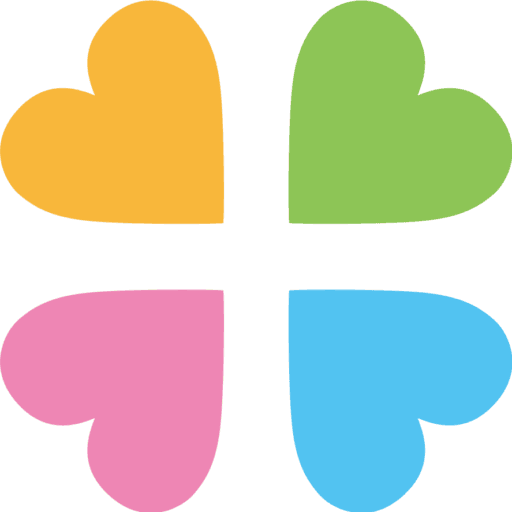
チェックポイント
症状は、皮膚症状、粘膜症状、呼吸器症状、消化器症状、神経症状、循環器症状に大きく分けられます。それぞれの代表的な症状は以下の通りです。
- 皮膚症状:蕁麻疹(じんましん)、かゆみ、赤み、むくみ、湿疹
- 粘膜症状:鼻汁(鼻水)、鼻閉(鼻づまり)、くしゃみ、口周りの違和感
- 呼吸器症状:咳、喘鳴(呼吸時にぜいぜいと雑音を発すること)、声枯れ、呼吸困難
- 消化器症状:嘔吐・はき気、下痢、腹痛
- 神経症状:頭痛、活気の低下、意識障害
- 循環器症状:血圧低下、不整脈、頻脈(心拍数が増加している状態)
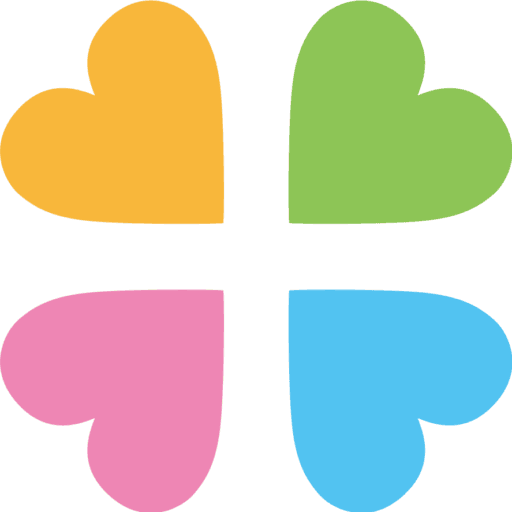
食物アレルギーの検査方法
食物アレルギーの特徴に続き、こちらでは食物アレルギーの検査方法をご紹介します。主な検査方法は、以下の通りです
- 血液検査
血液検査では、アレルギー反応に関わる物質「IgE抗体」が、どの食物に対してどれぐらいあるかを調べます。IgE抗体価はその値によってスコアで表示され、スコアが高いほど陽性度が強くなります。 - 皮膚プリックテスト
アレルギーの原因と疑われる食物の成分を皮膚につけて、専用の針で軽く刺激し、どのような反応がでるかを確認します。15分後に、蚊にさされたように赤く腫れていれば陽性の可能性が高いです。手軽にできるという利点がありますが、アレルギー反応が強いと全身に反応が起きる危険がありますので注意が必要です。 - 食物除去試験
原因と疑われる食物を1~2週間食べないようにして、症状がおさまるかどうかを確かめる検査です。症状がおさまった後は、確定診断のために食物負荷試験を行います。 - 食物負荷試験
食物除去試験の後に行う食物負荷試験は、実際に原因と疑われる食物を食べて、症状がでるかどうかを確かめる検査です。テストのやり方は病院によって様々です。
食物アレルギーの検査は、医師の指導の元に行わないと、症状が大きく出てしまうリスクがあります。アレルギーの反応が強い人は、必ず医師に一度相談することをおすすめします。

